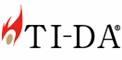3琉球王統の成り立ち(浦添王統から、尚氏)

沖縄の人が農耕を始めたのは10世紀頃だといわれている。
稲作を伴う農業の始まりは、人々の間に大きな変化をもたらしました。
農業のはじまり人口が増えてくると、共同体の平和と秩序を守るアジ(按司)と 呼ばれる有力者が登場してくる。
按司たちは各地でグスク(城)を築き、お互いに勢力の拡大を計るようになった。この激しい戦いの中から「アジの中のアジ」、「世の主」と呼ばれる政治的支配者が出現し、やがて自前の統一国家「琉球王国」を形成し、発展させることになる。
さて、ここで登場するのが浦添グスクを住んでいた、三大王、舜天、英祖、察度の中山王。
その頃になると、按司たちの統一がすすみ、沖縄本島の中部(中山)南部(南山)北部(北山)の三つの勢力が、それぞれグスクを拠点に勢力を競い合うようになります。これが沖縄歴史でいう三山時代です。
その中で一番の勢力をもっていたのが、中山王です。
なので、浦添中山王は、琉球王統の先駆け的な存在です。
浦添市民として誇らしいことです。
15世紀に入って台頭してきたのが、南部から兵を挙げた佐敷の按司、尚巴志という人です。
尚巴志は、三山のうち最も強大であった中山を滅ぼし、そして三山を統一して、ここに初めて琉球王国が誕生しました。
琉球の歴史では、後に、この王国が王位継続争いや護左丸、阿麻和利の乱などから弱体化し、内間金丸等によるクーデターにより、尚巴志王統が滅びたことから、尚巴志系を「第一尚氏王統」と呼び、内間金丸系を「第二尚氏王統」と区別しています。
これから約500年の及ぶ琉球王国が誕生しました。
「琉球」とう言葉は、中国の王様から頂いたもで、島国の琉球王国は大国である中国との友好な関係で成り立っていました。
関連記事